 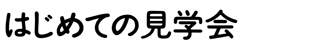
2011.8.20・21(土・日)大阪DTPの勉強部屋サマースクール
於:亮月写植室・某市施設会議室
●亮月写植室初の見学会でした
2011年8月20日から21日にかけて「大阪DTPの勉強部屋」さんがサマースクールと銘打ち、亮月写植室見学と勉強会のため筆者が住む街まではるばるお越しくださいました!
2011年春の写植機搬入直後に友人がお祝いに来てくれたことはあったものの、亮月写植室としては6月15日の設立以来初めてのご来訪でした。
20日午後、まずは亮月写植室の見学会。「関西には稼働する手動写植機は恐らく残っていないだろう」とのことで物珍しさもあってか、大幅に予定時間を超えてのご滞在となりました。筆者の写植に関する簡単な説明の後、写植機や所蔵の資料をご覧いただき、一人一人が実際に PAVO-JV という機種を操作して印字を体験していただきました。
写植機そのものを見たことがない方からかつてオペレータだった方まで、それぞれの立場から生きた写植に触れていただくことができたと思います。
見学会終了後は市の施設の会議室に会場を移し勉強会。
「写真植字がある日常。」と題して、筆者がどのように書体に興味を持ち、写植へと惹かれていったのか、写植の魅力は何なのか、写植にどのような想いを持っているのかを1時間強話させていただきました。
その後は参加された方一人ずつによるトークセッション。「私の仕事」をテーマにそれぞれの立場から発表され、一歩踏み込んだ内容を興味深く拝聴しました。翌日の午前中も同様でした。
1日目終了後は近くの居酒屋で懇親会。ざっくばらんな面白いお話を色々と伺うことが出来ました。
このような流れでした。参加された方がブログや動画として当日の様子をレポートしてくださっているので、そちらをご覧いただけたらと思います。(あまり大っぴらになるのも何なのでリンクは控えます。)
●ミニ取材・写植関連質疑応答
そういう訳で本稿では、主に懇親会中に質問させていただいた写植関連の話題をお届けしたいと思います。写植時代を知る何人かの方からご教示いただきました。
1番目の質問に関しては「なんでやねんDTP」の大石十三夫さんから後日詳しい解説のメールを送っていただきましたので、文意が変わらない程度に補筆して掲載します。
●1 画面のない手動写植機でもツメ印字をしていましたか? していたとすればどのように?
ツメ文字盤がない(使えない?)頃(モリサワ MM-II 使用=MC-6 の後継)は、
タイトルなどは少しツメ気味に均等字送りで印字し、現像後、アキを測って、再度ツメながら印字していました。
小さい本文組みや、あまりツメツメにする必要の無い小見出しなどは、32Qの枠(30Q大)にあらかじめ仮名類を印字したモノを利用し、30Q大の枠とのアキを計測しておき、級数に応じて比率でツメ歯数を換算して印字(最小駆動単位は1歯)。
32Qの文字に対して枠を30Q大としたのは、字送りベタで打った場合、32Q印字の際には2歯程度のアキが確保されるからです。
また、本文の完全箱組みなどまた違った方法を採りました(基本的に改行位置も決まっていますので)。
ツメ文字盤が使えるような場合でも、タイトルなどシビアなツメが要求されるモノはやはり一度ツメ文字盤通り(あるいはややツメ気味)に印字し、同じようにアキを計測して、再度印字したのだろうと思います(この場合は手作業での戻し量は少なくて済みます)。推測ですが。
私の場合はツメ文字盤を使えるようになるのは写研 PAVO-KVB(ディスプレイ有り)を使うようになってから……つまりモリサワから写研に転向してからでした。写研に転向したのはディスプレイが付いたのと書体の問題が大きかったためです。
蛇足ですが、本文組みはツメ文字盤の送りで、経験による食い込みツメ量を戻しながら空印字していました。
このとき、行末とのアキをSP(スペース)で分割(行長より短い場合)、あるいは行末を超えて空印字し、JQレンズがセットされるのを元のQ数に戻して本チャン印字。行長が20字程度あれば半角程度のオーバーなら0.4em程度のツメ量オーバーなので大丈夫です。
この時に空印字の II を使いました。手作業での戻し量などは機械に記憶されています。
広告が主ですので、改行位置などに気を遣うモノでした。
(以上大石さん)
●2 写植時代はオペレータに組版に対する教育がされていたという印象を持っていますが、実際はどうだったのでしょうか?
「写植機1台買えば1人写植教室に行かせてもらえる」のですが、写植教室で習うのは写植機の操作や基本的な組み方だけで、組版に関するルール等発展的なものは実務の中で先輩から教えてもらったり学んだりすることが多かったとのことでした。
●3 写植オペレータってやはり儲かるものだったのでしょうか?「写植でビルが建つ」という話を伝説のように見聞きするのですが。
確かに儲かったそうです。1970年代は写植の仕事が多かったとのこと。技術があればできる仕事だったので、勤めで入った会社を辞めて独立するのはもちろん、「流し」であちこちの会社を廻るような人もいたらしい。徹夜は当たり前で時給換算数千円の世界だったそうです。
但し電算写植は儲からなかったとか。
●4 何故写植は(特に若い人が)注目しないのでしょう? 活版はブームとまで呼ばれ、愛好家がいるだけでなく仕事として成り立っている人達がいる中で、それより新しい技術の写植が中抜けのように素通りされるのは何か理由があるのでしょうか?
一つ目の理由として、活版のように活字が直接印刷物の文字となるのではなく、写植はあくまで製版の為の部品のようなものだから。
印字された写植の印画紙があったとしても写植時代に行われていたワークフローは非常に手間隙や金銭の負担がかかり、現在DTPで用いられるワークフローを使用せざるを得ない。しかしこれではスキャンする等しないと写植の文字は使用できない。つまり書体以外に写植である利点がないということです。
二つ目の理由として、写植システムを維持していくことが困難だから。
写真植字機自体が既に生産終了となって久しく、メンテナンスが難しくなってきています。また、現像液は劣化が非常に早く、業務の中では1週間も使わずに交換する必要があります。
このような状況の中、仕事の頻度に対し写植を生かしておくことが不採算となれば、たとえこれまでたまに受注があったとしても廃業せざるを得なくなるのです。
つまり、印刷用の文字として直接使うことはもはや不可能と言ってよい状態で、維持にコストがかかり過ぎる、というのが業として成り立たない理由ではないか、ということでした。
写真植字そのもの(機械や歴史等)に興味を持つ若い世代の人が殆どいない理由については分からずじまいでした。
この質問から発展して、活版の印圧やマージナル・ゾーン、写植のぼけ足を過剰に有難がることについて手厳しい見解が出され、なかなか胸の透く思いがいたしました。このことについてはまた別の機会に……。
*
写植機は実用を始めたばかり、個人サークルとしても設立したばかりという時期だった為見学も講演も全くと言っていい程蓄積されたものがありませんでしたが、不慣れながら筆者も楽しませていただきました。皆さん本当にありがとうございました!
【完】
→写植レポート
→メインページ |

